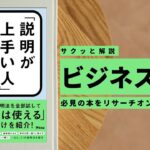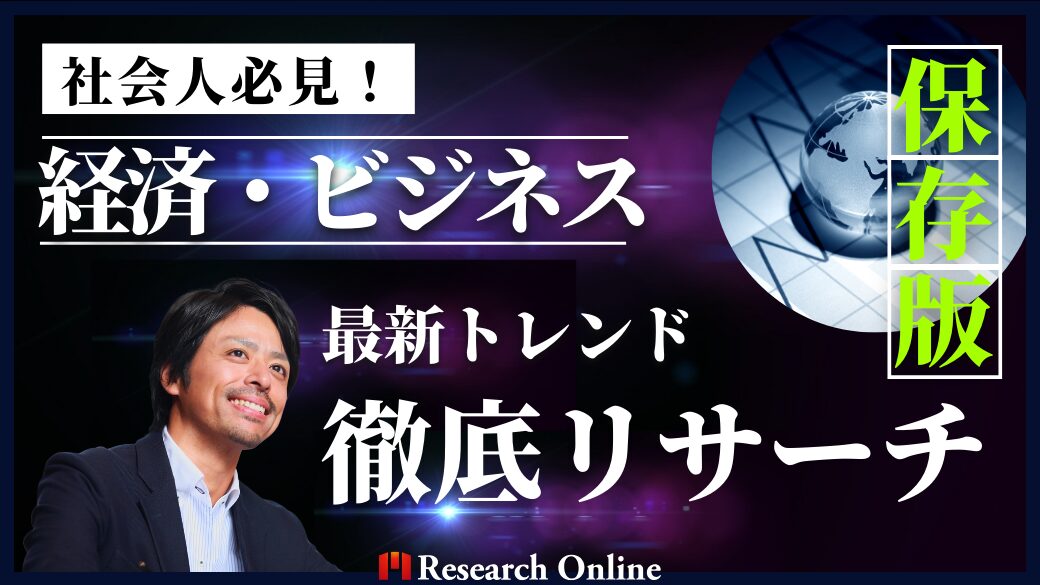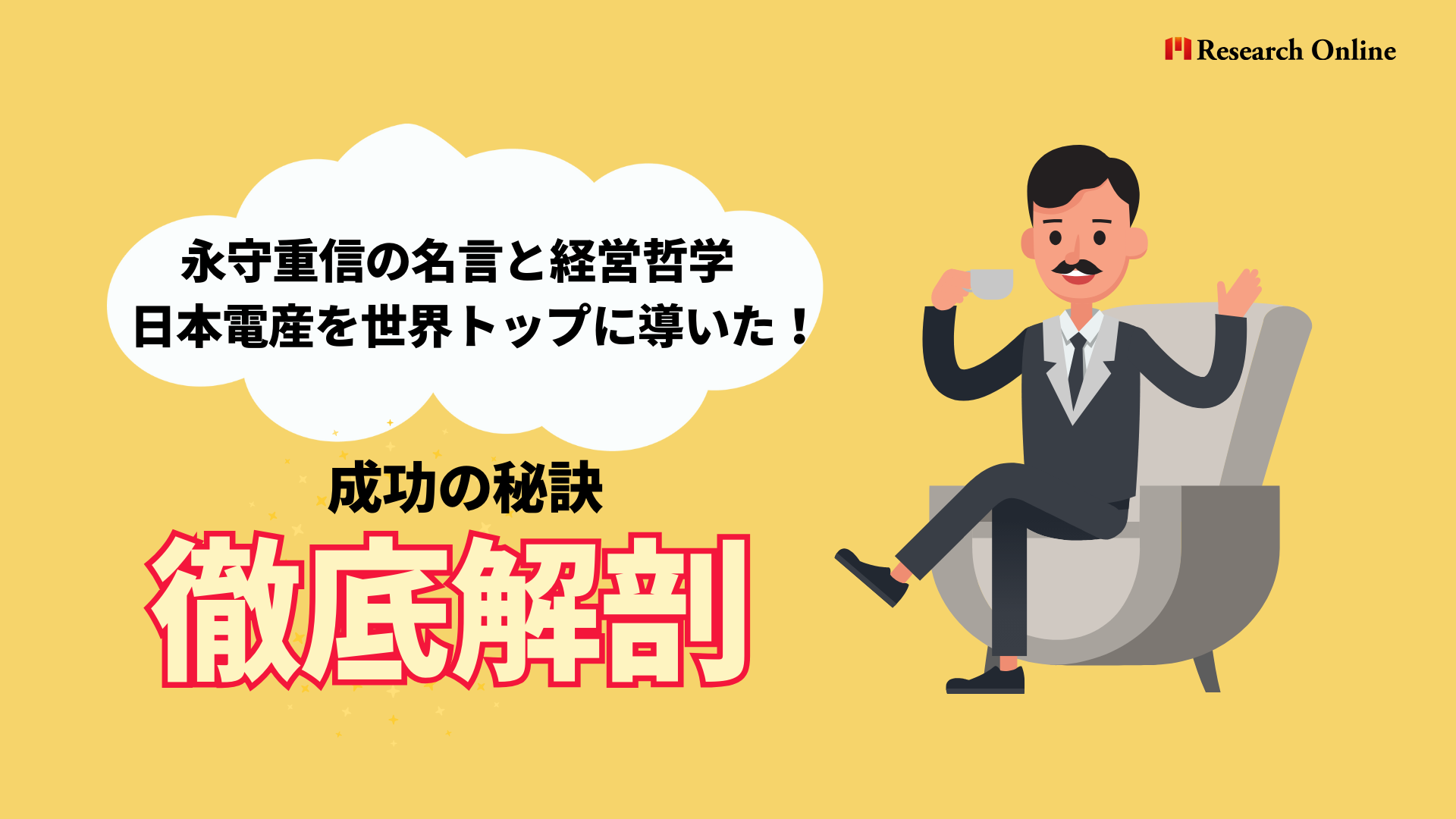
この記事の目次
はじめに
小さな町工場から一部上場企業にまで成長した日本電産の創業者の永守重信氏は独創的な発想を持ち、行動されるリーダーとして知られています。 素晴らしい名言も知られており、多くの経営者が指針としているカリスマとしても知られています。 今回は永守重信氏の名言として知られている7つを特にピックアップして皆様にご紹介したします。永守重信の経営スタイルと日本電産の成功物語
 日本電産の創業者である永守重信は、世界トップクラスのモーターメーカーに育て上げるために仕事に対しての正しい取り組みを徹底してきました。
単にがむしゃらに長時間働くことではなく、いかに改善点を見つけて効果的に会社が変化していくべきかを強調しています。
社員が細かなところで自分の発想によって工夫をし、情熱と熱意を注いでいくことを理想の働きとしています。
生産性向上はどの企業においても大きなテーマであり、働き方改革によって残業時間の半減に成功したという企業も少なくありません。
ハードワークをしながらも長時間労働ではない働き方が今後さらに注目されるものです。
永守重信がどういった哲学を持っているのかを知ることは仕事への取り組みに影響を及ぼすかもしれません。
今現在の仕事の取り組み方に疑問を抱くことが多いのであればなおのこと永守重信の仕事への取り組み方を学び、今後に役立てて今までの自分から新しい自分をつくっていきましょう。
日本電産の創業者である永守重信は、世界トップクラスのモーターメーカーに育て上げるために仕事に対しての正しい取り組みを徹底してきました。
単にがむしゃらに長時間働くことではなく、いかに改善点を見つけて効果的に会社が変化していくべきかを強調しています。
社員が細かなところで自分の発想によって工夫をし、情熱と熱意を注いでいくことを理想の働きとしています。
生産性向上はどの企業においても大きなテーマであり、働き方改革によって残業時間の半減に成功したという企業も少なくありません。
ハードワークをしながらも長時間労働ではない働き方が今後さらに注目されるものです。
永守重信がどういった哲学を持っているのかを知ることは仕事への取り組みに影響を及ぼすかもしれません。
今現在の仕事の取り組み方に疑問を抱くことが多いのであればなおのこと永守重信の仕事への取り組み方を学び、今後に役立てて今までの自分から新しい自分をつくっていきましょう。
日本電産の賃金改革:永守重信の労働者への思い
永守重信は昨年10月に、日本電産の従業員の賃金を今後3年間で30%引き上げると発表し話題になりました。
生産性向上や原価低減活動で確保した利益の一部を従業員に還元する考えです。
また従来の年齢や勤続年数ではなく、実績に応じて5段階で評価する制度を導入すると説明しました。
評価がもっとも低い人でも従来と同じくらい賃金をもらえることを理想にし賃金の水準は下げない方針を示しています。
給料アップは嬉しいですが、その分、税金も上がってしまうので気になりますよね。
税金関連に対する記事はこちらをチェック。
ビジネスマンに響く永守重信の経営哲学
 ビジネスマンにとって永守重信の哲学は心に響くものです。
他社よりも柔軟な対応をしながら経営をしていき、自由に自分の頭を使って仕事を取り組むべきであるのを理解して実践しています。
いかに無駄を削減するかはどのビジネスマンにとってのテーマであるのは間違いありません。
無駄を削減するには何が無駄であるかについて可視化できるようにしないといけないものです。
永守重信は何が無駄であるかについて把握するためにさまざまなアイディアを駆使しています。
永守重信の経験から基づく哲学は多くのビジネスマンが唸る内容となっています。
人間の意志の力が仕事にどれだけの影響を及ぼすのかを永守重信は理解しています。
ちゃんと意志を持って仕事に取り組むことによってどういった変化があるのかを哲学からしっかりキャッチできて、今後にプラスになるかもしれません。
ビジネスマンの心に響く永守重信の哲学とはどういったものであるのかを知ったうえで今後の自分にプラスになることをしっかり吸収しましょう。
ビジネスマンにとって永守重信の哲学は心に響くものです。
他社よりも柔軟な対応をしながら経営をしていき、自由に自分の頭を使って仕事を取り組むべきであるのを理解して実践しています。
いかに無駄を削減するかはどのビジネスマンにとってのテーマであるのは間違いありません。
無駄を削減するには何が無駄であるかについて可視化できるようにしないといけないものです。
永守重信は何が無駄であるかについて把握するためにさまざまなアイディアを駆使しています。
永守重信の経験から基づく哲学は多くのビジネスマンが唸る内容となっています。
人間の意志の力が仕事にどれだけの影響を及ぼすのかを永守重信は理解しています。
ちゃんと意志を持って仕事に取り組むことによってどういった変化があるのかを哲学からしっかりキャッチできて、今後にプラスになるかもしれません。
ビジネスマンの心に響く永守重信の哲学とはどういったものであるのかを知ったうえで今後の自分にプラスになることをしっかり吸収しましょう。
永守重信の三大精神:情熱、熱意、執念
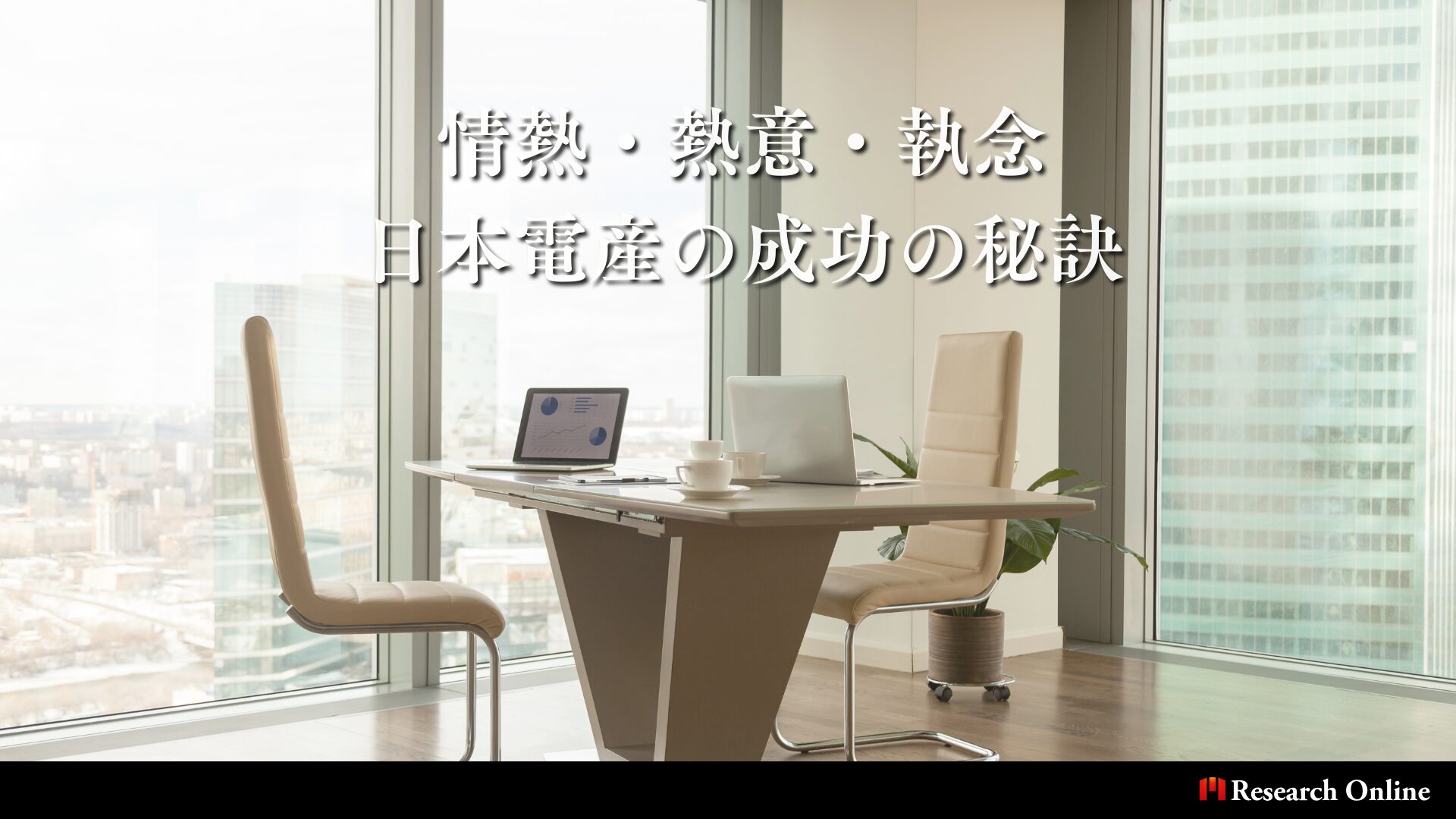 永守重信が経営を行う日本電産の三大精神は情熱・熱意・執念です。
創業した当初は零細企業であり、競争相手は日本を代表する巨大企業で、どう戦うべきかを考えないといけませんでした。
そしてより多くの時間を働いて売上高が1兆円となったときに、働き方改革を行うことになります。
優秀な人材が集まってくるようになってからは働く時間の長さで勝負するのではなく、生産性を上げて勝負をしていくことになりました。
残業を0時間にすることはあくまでも手段であり、根本的には生産性をいかに上げるかが重要と永守重信は考えています。
海外の企業では基本的に残業はありません。
それでいて日本企業よりも生産性が高いのは、働き方を統一化しているためです。
無駄をなくすことによって残業時間がなくなるものの、投資をしないといけない場合もあるものです。
いかに生産性を上げるかが今後企業として生き残っていくかどうかのポイントであり、永守重信の三大精神について知っていくことに意味があります。
永守重信が経営を行う日本電産の三大精神は情熱・熱意・執念です。
創業した当初は零細企業であり、競争相手は日本を代表する巨大企業で、どう戦うべきかを考えないといけませんでした。
そしてより多くの時間を働いて売上高が1兆円となったときに、働き方改革を行うことになります。
優秀な人材が集まってくるようになってからは働く時間の長さで勝負するのではなく、生産性を上げて勝負をしていくことになりました。
残業を0時間にすることはあくまでも手段であり、根本的には生産性をいかに上げるかが重要と永守重信は考えています。
海外の企業では基本的に残業はありません。
それでいて日本企業よりも生産性が高いのは、働き方を統一化しているためです。
無駄をなくすことによって残業時間がなくなるものの、投資をしないといけない場合もあるものです。
いかに生産性を上げるかが今後企業として生き残っていくかどうかのポイントであり、永守重信の三大精神について知っていくことに意味があります。
永守重信の名言7選:経営者の指針となる言葉
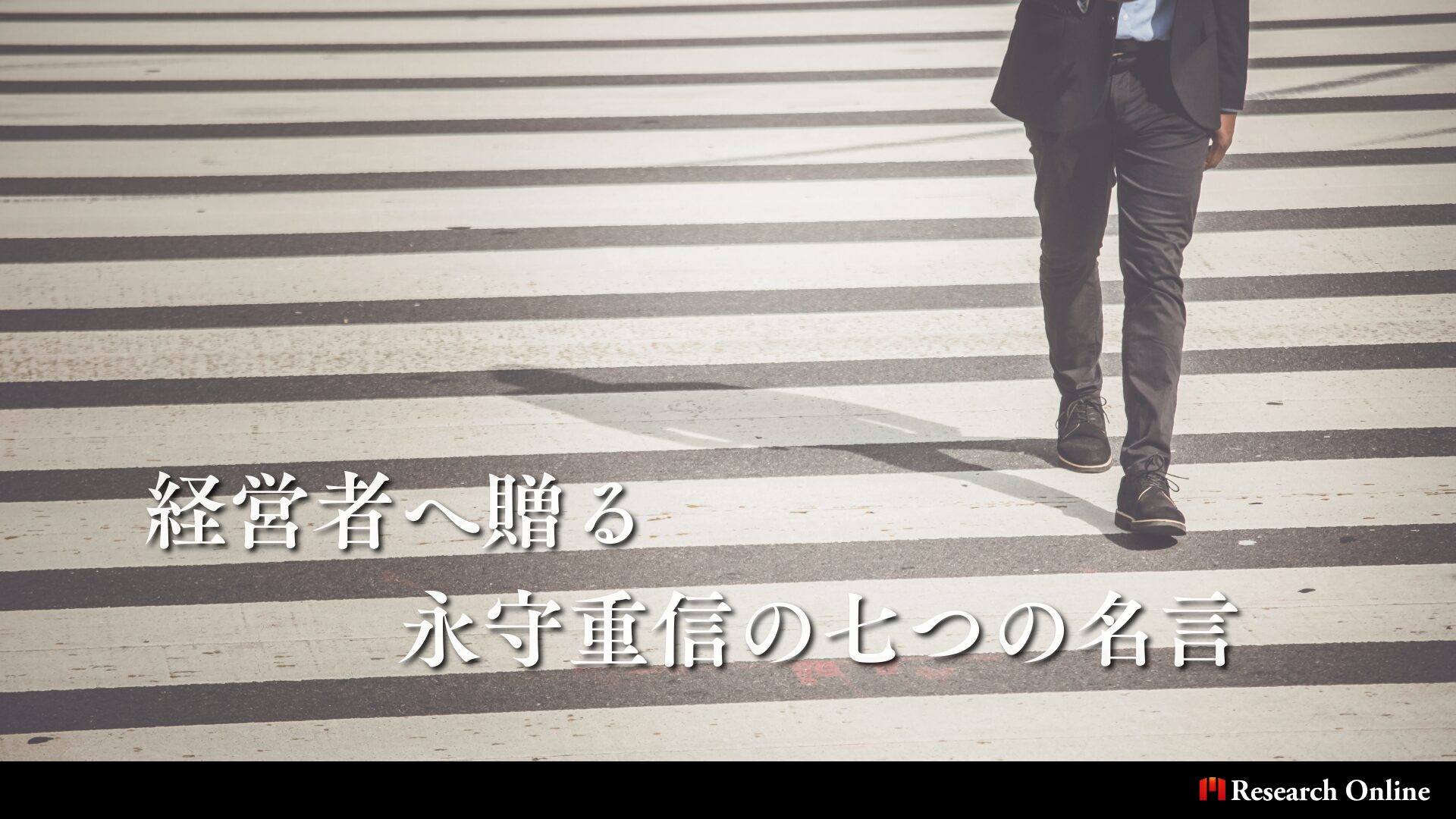 永守重信には大きく分けると7つの名言があります。仕事に取り組むにあたっての姿勢や今何をすべきかについて見直すきっかけになるかもしれません。
そしてなぜ永守重信が優秀な経営者であるかを知ることもできます。
永守重信には大きく分けると7つの名言があります。仕事に取り組むにあたっての姿勢や今何をすべきかについて見直すきっかけになるかもしれません。
そしてなぜ永守重信が優秀な経営者であるかを知ることもできます。
永守重信の名言1.
「リターンを早く求めたいからすぐ首を切る、資産を売却する。 そうすることで企業価値は確かに上がるかもしらんけど、多くの従業員の生活が犠牲になる。 従業員の首を切ってまで利益を上げなくてはならなかったら、僕は辞めます。」 永守重信は従業員に対して無理をさせて企業価値を上げることに疑問を抱いています。 いかに従業員の生活を犠牲にすることなく、生産性を上げることによって企業価値を上げることを重要と考えています。 授業員の首を切ることをできるだけしない方針を示しています。永守重信の名言2.
「学ぶ機会、場所はどこにでもある。 起きていることをボヤッと見過ごしてはダメだ。その裏に何があるのか、どうしてそうなるのかをいつも考えることが必要だ。 」 どの分野においても学ぶ機会と場所はどこにでもあり、今世の中で何が起きているのかをしっかり見極めていかないといけないということを永守重信は提言しています。 インターネット全盛の時代になったことで、自ら行動して考えないといけないということを理解した方がよいでしょう。永守重信の名言3.
「大事なのは『常に』、そして『徹底して』経営を動かし続けること。 」 常に徹底して経営をしていくことに意味があると永守重信は考えています。 状況の変化にいかに対応していかないといけないかがそれぞれの企業のテーマです。 いかに軸をブレずに今後状況の変化に対応していくことに注視しているといえるでしょう。永守重信の名言4.
「失敗だけが人間の筋力をつくります。 精神力を付けて人間の幅を広げていく。人間の器を大きくする。成功ではなく失敗が器を大きくする」 失敗することによって人間としての幅が広がっていき、さらに成長していくと提唱しています。 成功によって得られるものよりも失敗することによって得られるものの方が大きく、そのためには失敗を恐れずにチャレンジすることが大事であることを重要としています。永守重信の名言5.
「『1兆円になったばかりの会社が10兆円なんて、おかしいですよ』と笑う人もいます。 おかしいと思うならそれでいい。創業社長なんて、みんなおかしいものです。」 創業社長として経営が順調にいくことによって大きな可能性があることを示しています。 この可能性をおかしいことであると考えるのではなく、可能性があることをしっかり理解した方がよいといっているものです。永守重信の名言6.
「仕事のやり方も日々、見直しています。 長年やってきた仕事のやり方の『無駄の多さ』に、愕然とする日々です。 」 仕事の取り組み方で重要であるのは無駄を省くことであり、日々見直すべきであることを提唱しています。 無駄を省くことによって生産性が上がって従業員も無理をする必要がなくなり、企業としての価値も上がっていくといえるでしょう。永守重信の名言7.
「私たちの会社は『1兆円企業』になった。 世界で勝てる『10兆円企業』を目指すなら、変わらなければならない。脱皮しない蛇は死ぬ。 」 さらに企業として成長するためには上を目指すべきで、常に変わっていく状況に対応するために、企業として変わっていく姿勢を持たないといけません。 1兆円企業になったことに胡坐をかくのではなく、さらに上を目指さないと世界では戦えないことを示しています。永守重信の言葉の力:ビジネスマンの心に響く名言
永守重信の名言はビジネスマンとして、企業としてどうあるべきかを示すものです。 今現在の状況に甘えることなく、自分が何をすべきかを今一度考えてみてはいかがでしょうか? 自己管理をするのは簡単ではないものの、今現在の状況において何が無駄であるかを考えて省いていくことを考えないといけません。 一生懸命頑張ることは当然とし、いかにより効率的効果的に働いていけるかといった仕組みを考えるのが望ましく、妥協しないことを重視しています。