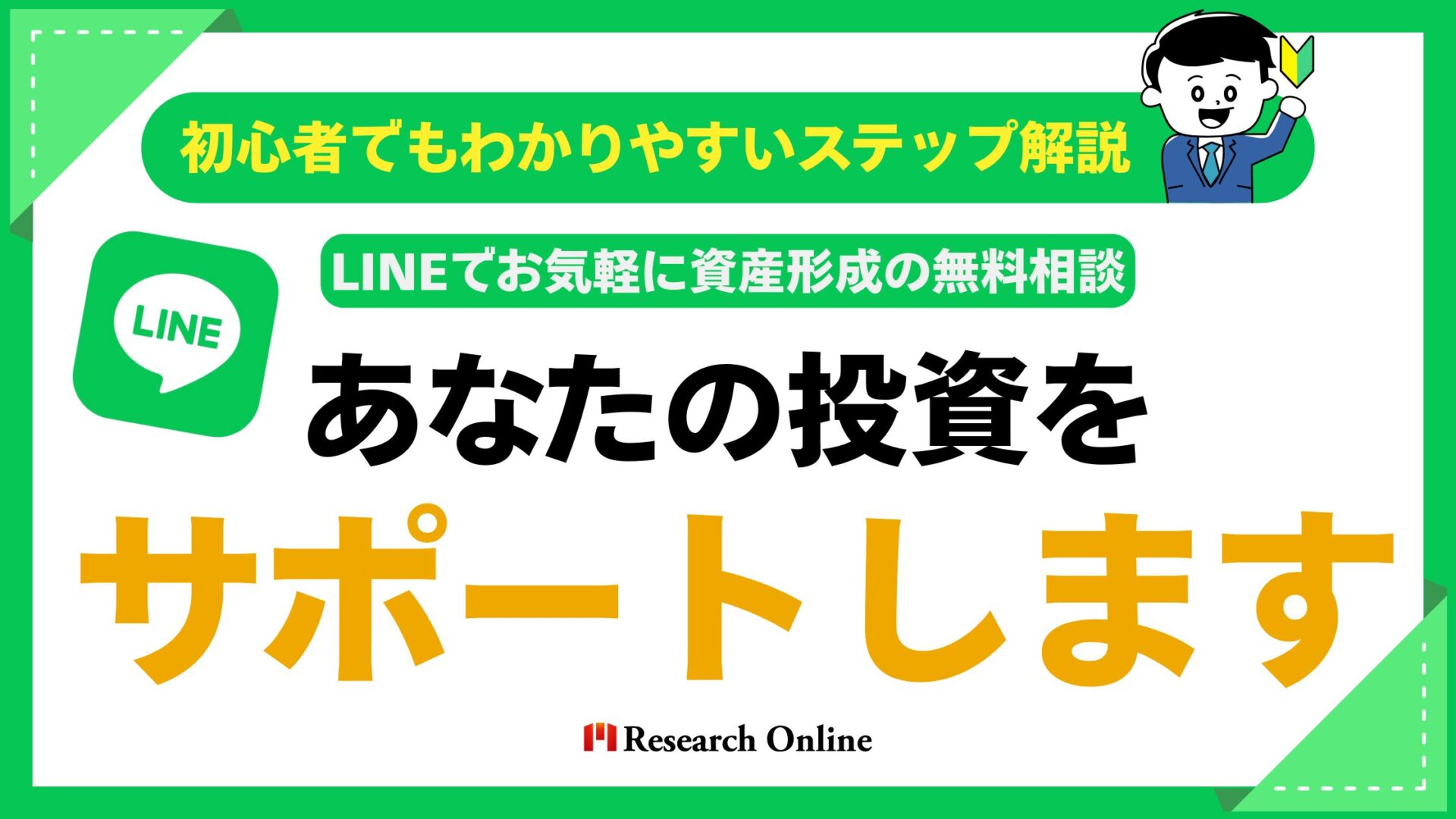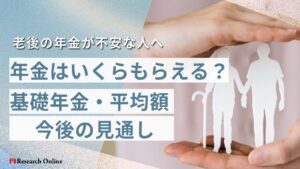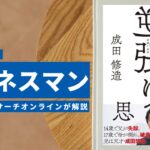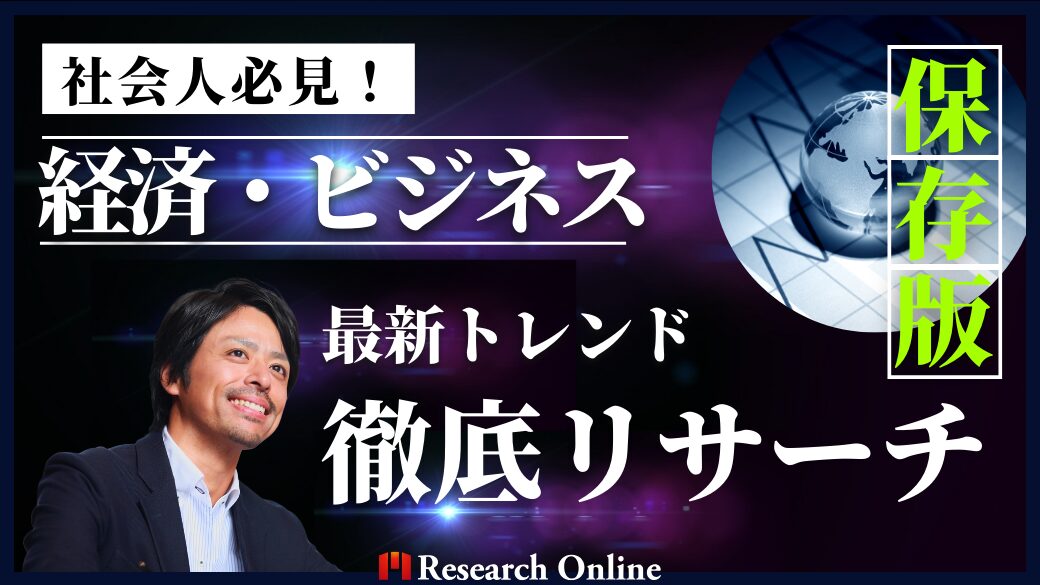贈与税や相続税は、「高いものをもらったとき」だけでなく、「安く買った」「高く売った」といった取引でも発生することがあります。国税庁のルールは一見シンプルですが、実際の課税はケースごとに判断されるため、非常にわかりにくいのが特徴です。ここでは、具体例を交えながら整理してみましょう。
この記事でわかること
-
贈与税がかかる基本ルールと非課税枠110万円の仕組み
-
安すぎる・高すぎる売買が「みなし贈与」になるケース
-
相続開始前の贈与が持ち戻し対象となる最新ルール(最長7年)
-
親族間と第三者間、法人が絡む取引での課税の違い
-
贈与税・相続税トラブルを避けるための実務的な対策方法
記事の3点要約
-
贈与税は「もらう」だけでなく「安く買う・高く売る」取引でも発生する可能性がある。
-
国税庁は明確な基準を示していないが、実務上は時価の8割以上が安全ラインの目安。
-
2024年以降は相続前の贈与が最長7年間持ち戻しの対象となるため、長期的な資産設計が重要。
📱悩んだら、リサーチオンラインに相談して解決📱
この記事の目次
贈与税の基本をおさらい
💰 贈与税の基本をおさらい
知っておきたい贈与税の仕組みと基礎控除
贈与税は、個人が個人から財産をもらったときにかかる税金です。 1年間に受け取った贈与の合計から、まず110万円の基礎控除を差し引きます。 これを超えた部分が課税対象となり、税率は10%から最大55%まで段階的に上がっていきます。
📊 贈与税の計算の仕組み
年間の贈与額
200万円
例:現金贈与
基礎控除額
110万円
誰でも使える
課税対象額
90万円
この部分に課税
税率は贈与額に応じて段階的に上昇
少額の贈与
年間110万円以下なら
贈与税は0円
申告も不要でお手軽
大きな贈与
110万円を超えると
超過分に10〜55%の税金
確定申告が必要
💡 具体例で理解しよう
例:300万円の贈与を受けた場合
① 300万円 − 110万円(基礎控除)= 190万円(課税対象)
② 190万円 × 10%(税率)= 19万円(贈与税)
③ 実際に受け取れる金額:300万円 − 19万円 = 281万円
つまり、「少額なら課税されないけれど、
大きな贈与にはしっかり税金がかかる」という仕組みです。
「安すぎる売買」が贈与になるワケ
⚠️ 「安すぎる売買」が贈与になるワケ
時価との差額が贈与税の対象に!
💡 具体例で理解しよう
時価
120万円
売買価格
1,000円
差額
119万9,000円
贈与税額:約1万円
支払額と時価との差額である119万9,000円が"実質的に贈与を受けた"と判断される可能性があります。
📊 売買価格の目安とリスク度
ただし、国税庁は「いくら以下ならアウト」と明確な基準を示していません。
そのため、実務上は次のような目安がよく使われます。
| 時価に対する売買価格 | リスク度 | コメント |
|---|---|---|
| 90%以上 | 低い | 指摘されにくい |
| 80%台 | 注意 | 証拠(査定・鑑定)があると安心 |
| 70%台 | 高い | 贈与扱いされやすい |
| 60%以下 | ほぼアウト | 贈与認定の可能性大 |
⚠️ 最も注意すべきポイント
「明確なルールがない=ケースごとに判断される」という点が、納税者にとって最もややこしい部分です。
親族間取引は特に注意が必要で、第三者との取引よりも厳しく見られる傾向があります。
具体例で理解する
💡 具体例で理解する
低額譲渡・高額売却の落とし穴
1億円の品を9,000万円で購入
低額譲渡のケース
時価
1億円
購入価格
9,000万円
売買価格は時価の90%
一見"9割の価格で買っているから問題ない"と思えますが、差額の1,000万円が大きいため、税務署に目を付けられる可能性は否定できません。
仮に贈与とみなされた場合
贈与税:約231万円
⚠️ 割合は高くても差額が大きいと要注意
100万円の品を200万円で売却(親族間)
高額売却のケース
時価
100万円
売却価格
200万円
売却価格は時価の200%
売主が通常より高くお金を受け取った形になるため、差額の100万円を「贈与」と指摘されるケースがあります。
📝 親族間 vs 第三者間の違い
第三者同士の売買なら譲渡所得として扱われるのが一般的ですが、親族間取引は贈与の意図を疑われやすくなります。
⚠️ 高額売却も贈与税の対象になりうる
相続との関係(2024年改正)
🆕 2024年改正
🏛️ 相続との関係(2024年改正)
贈与の持ち戻し期間が大幅延長
贈与は「相続税の逃げ道」として使われやすいため、2024年からルールが強化されました。 従来は「亡くなる3年前までの贈与」を相続財産に持ち戻す仕組みでしたが、今後は最長7年分まで加算されます。
📊 改正前後の比較
改正前(〜2023年)
3年
相続開始前3年以内の
贈与を相続財産に加算
改正後(2024年〜)
7年
相続開始前7年以内の
贈与を相続財産に加算
💰 ただし救済措置あり!
100万円控除
4〜7年前の贈与については合計100万円まで控除されるため、
小額贈与への配慮は残されています。
持ち戻し期間の詳細
全額加算
0〜3年前の贈与
100万円控除あり
4〜7年前の贈与
⚡ この改正による影響
- 相続税対策としての駆け込み贈与が難しくなる
- より長期的な視点での資産承継計画が必要
- 年110万円以下の贈与でも7年分は相続財産に加算される可能性
改正により相続税対策はより計画的に行う必要があります。
ただし、小額贈与への100万円控除により、
過度な負担増は避けられる仕組みになっています。
法人が絡む場合の注意
🏢 法人が絡む場合の注意
個人間とは異なる課税ルール
法人が相手になるとルールはまた変わります。
個人同士の贈与とは課税の仕組みが違うため、専門的な判断が必要になります。
法人→個人
贈与税ではなく、給与所得や一時所得として扱われます
💡 役員・従業員なら給与所得
💡 それ以外なら一時所得
個人→法人
法人は受贈益として法人税が課税されます
個人側に譲渡所得が生じる可能性があります
法人の寄附金
限度額を超えると経費として認められず、損金不算入扱いになります
⚠️ 限度額超過分は法人税の対象
📊 課税関係の早見表
重要なポイント
個人同士の贈与とは課税の仕組みが違うため、
ここでも専門的な判断が必要になります。
特に法人が絡む取引は税務調査の対象になりやすいので注意が必要です。
トラブルを避けるには
🛡️ トラブルを避けるには
贈与税問題を防ぐ5つの対策
-
1
契約書をきちんと残す
売買か贈与かを明確に記載した契約書を作成しましょう。 口約束では後で問題になる可能性があります。
💡 必要な記載事項
- • 当事者の氏名・住所
- • 対象物の詳細(不動産なら所在地・面積等)
- • 売買価格または贈与の意思表示
- • 契約日・引渡日
-
2
時価の証拠を準備する
鑑定書・査定書・見積書など、客観的な時価を証明できる書類を準備しておきましょう。
📄 有効な証拠書類
- • 不動産:不動産鑑定士の鑑定書
- • 自動車:中古車買取業者の査定書
- • 美術品:専門家の評価書
- • 株式:証券会社の時価証明書
-
3
振込記録や領収書を保存しておく
支払いの証拠となる振込記録や領収書は必ず保存しましょう。 現金での取引は避け、記録が残る方法を選びます。
現金手渡しは証拠が残らないため、税務調査で不利になる可能性があります。必ず銀行振込など、記録が残る方法を使いましょう。
-
4
その年の贈与は合算して110万円以内に収める
1年間(1月1日〜12月31日)に受けた贈与の合計額が110万円以内になるよう管理しましょう。
📅 年間管理のポイント
- • 複数の人からの贈与も合算される
- • 現金以外の財産も時価で計算
- • 年末には残額を確認して調整
-
5
将来の相続を見据えて、持ち戻しルールも考慮する
2024年改正により、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます。 長期的な視点で計画を立てましょう。
ただし、4〜7年前の贈与については100万円の控除があるため、小額贈与への配慮は残されています。
プロからのアドバイス
これらの対策をすべて実行することで、
税務調査があっても慌てることなく対応できます。
特に親族間の取引では、より慎重な準備が必要です。
✅ 対策チェックリスト
✓
契約書作成
✓
時価の証明
✓
記録の保存
✓
110万円管理
✓
長期計画
FAQ|贈与税・相続税
FAQ|贈与税・相続税
よくある質問と回答
-
Q.1 贈与税は110万円以下なら絶対にかからないのですか?
A. 基本的に1年間で受けた贈与の合計が110万円以下であれば課税されません。ただし、同じ年に複数の人から贈与を受けた場合は合算されるため、合計が110万円を超えると申告が必要です。
-
Q.2 安すぎる価格での売買は必ず贈与税の対象になりますか?
A. 必ずではありません。国税庁は明確な数値基準を設けていませんが、時価の8割以上なら比較的安全とされ、7割程度になると贈与と判断されるリスクが高まります。最終的には個別事情や時価の根拠によって判断されます。
-
Q.3 親族間と第三者間の取引では課税の扱いは変わりますか?
A. 変わります。親族間では「贈与」と判断されやすく、差額が贈与税の対象になるケースが多いです。一方、第三者との取引では通常「譲渡所得」として扱われることが多いです。契約書の有無や内容も重要な判断材料になります。
-
Q.4 相続開始前の贈与はすべて持ち戻し対象ですか?
A. 2024年からは相続開始前最長7年間の贈与が持ち戻しの対象になります。ただし、4〜7年前の贈与については合計100万円まで控除があるため、小額なら影響を受けにくい仕組みです。
-
Q.5 法人から財産をもらった場合も贈与税がかかりますか?
A. いいえ。法人からの財産移転に贈与税はかかりません。その代わり、受け取った個人には所得税(給与・一時所得など)がかかります。法人側は寄附金や経費計上の扱いが問題になることがあります。
重要な注意事項
贈与税・相続税は複雑な税制です。実際の取引や贈与を行う前に、必ず税理士等の専門家にご相談ください。
適切な税務対策により、合法的に税負担を軽減することができます。
早めの相談と計画的な対策が重要です。
まとめ
贈与税は「お金をもらったとき」だけでなく、「安すぎる売買」や「高すぎる売買」にも適用される、意外と奥の深い税金です。ルールが曖昧な部分が多いからこそ、時価の証拠と契約書を残しておくことが、後々のトラブルを避ける最善策になります。相続も見据えた長期的な資産設計をするなら、経験豊富な税理士に相談することを強くおすすめします。
出典
-
国税庁「贈与税がかかる場合(基礎控除110万円など)」
-
国税庁「個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」
-
国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税・持ち戻しルール)」
働く皆さんを応援しています!

あなたの資産形成を成功へ導きます
📊 投資の現状と課題
投資実施者の割合
まだ投資をしていない人
貯金重視の考えが根強い
😰 こんなお悩みありませんか?
政府は「貯金から投資へ」と言うけれど、何から始めればいいかわからない。iDeCoやNISAって聞くけど、複雑そうで不安...
✅ リサーチバンクが解決します!
iDeCoやNISAを活用した年金・税金対策の相談を提供し、多くの悩みを解決してきた実績があります。若いうちからの資産形成をしっかりサポート!
🎯 私たちのサービス
iDeCo相談
個人型確定拠出年金で老後資金作りと税制優遇を両立
NISA活用
少額投資非課税制度で効率的な資産形成をサポート
税金対策
節税効果を最大化する戦略的アドバイス
個別相談
あなたの状況に合わせたオーダーメイドプラン
📱 悩んだら、リサーチオンラインに相談して解決 📱
気軽に相談できる公式LINE「Research Online +Plus」を開設し、不安解消をサポートしています。
✨ 公式LINE登録のメリット