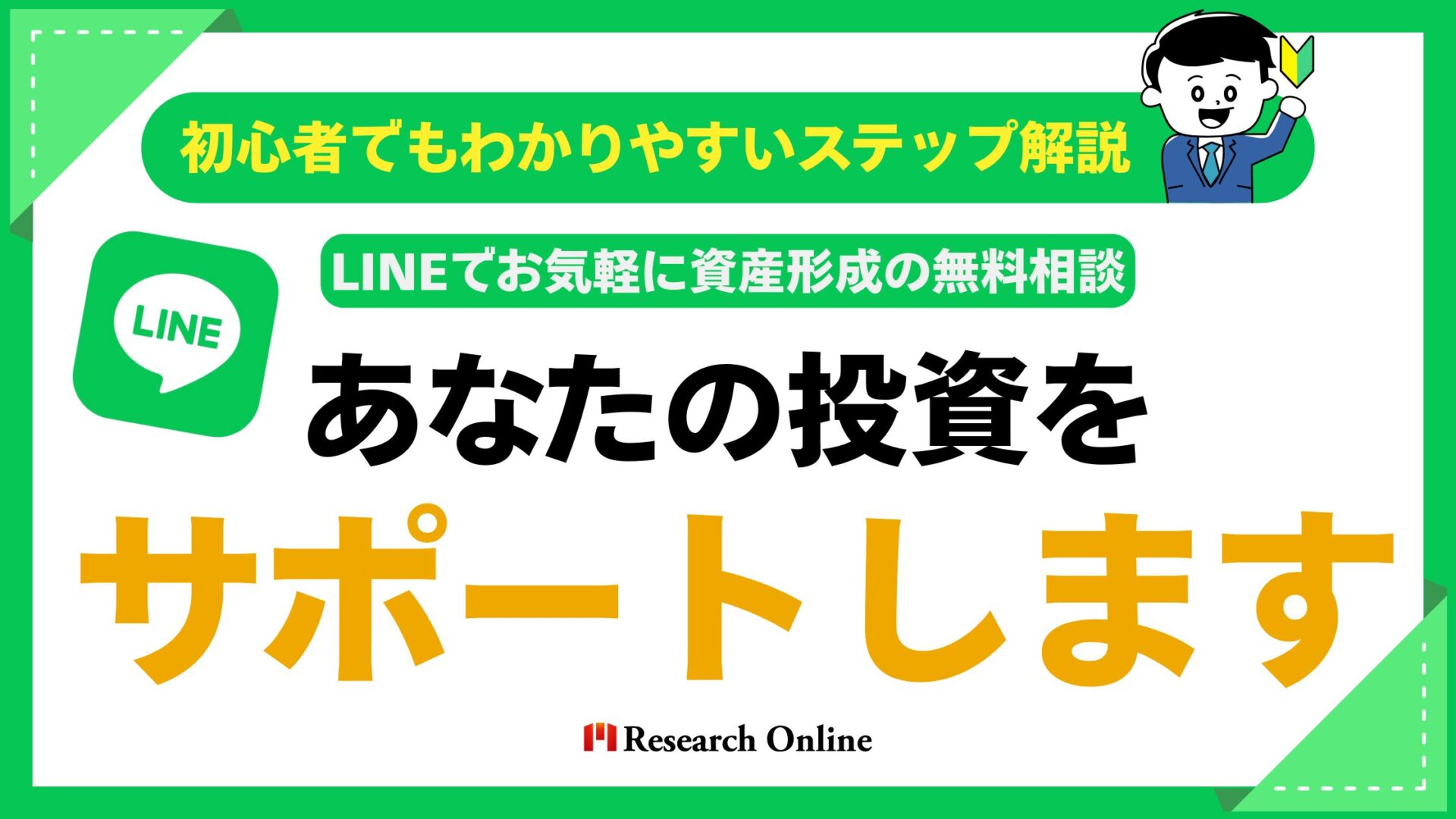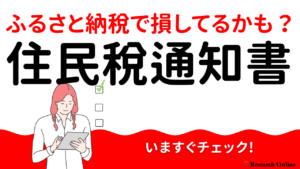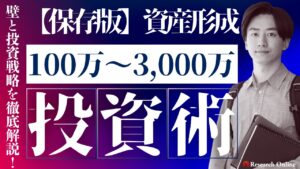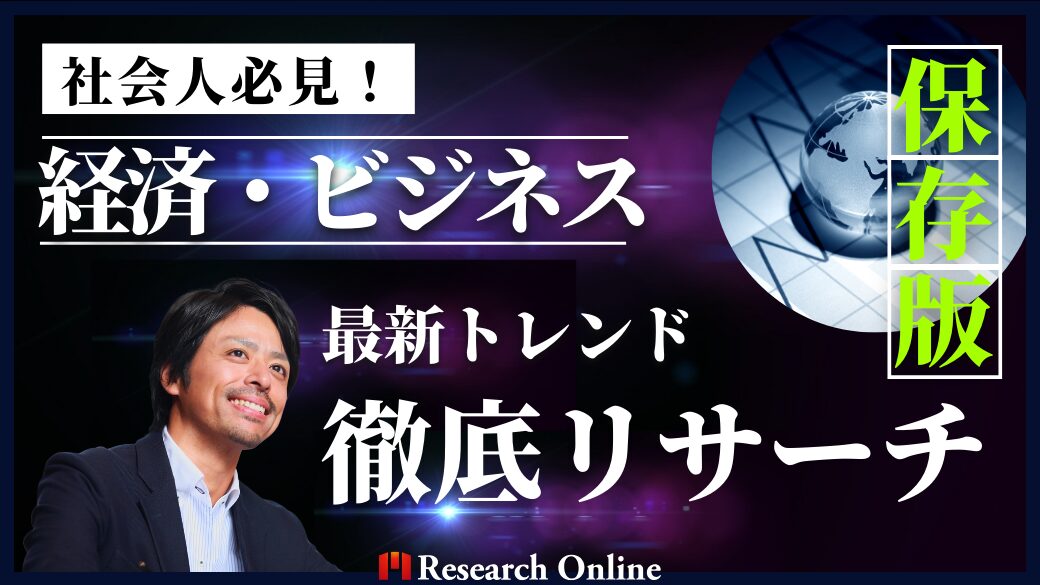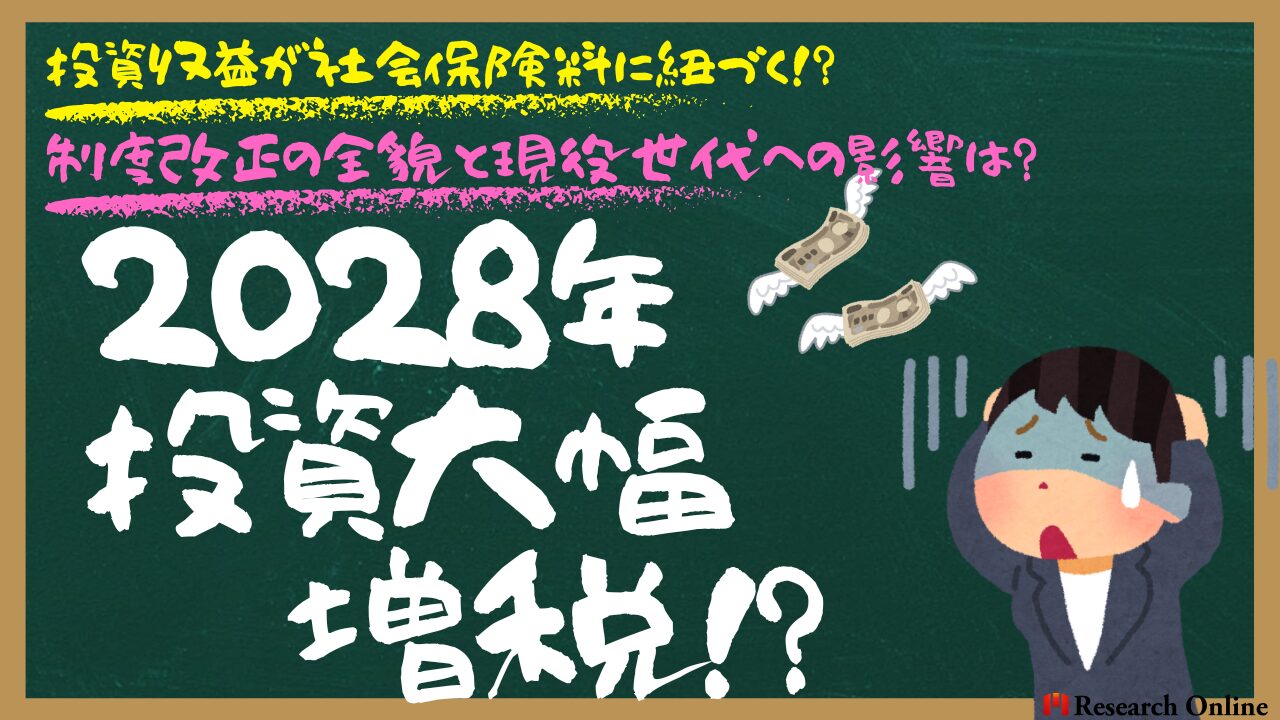
2025年の政府方針で、「配当金や売却益といった金融所得を社会保険料(医療・介護)に組み込む動き」が浮上しています。これまで社会保険料は“給与収入”に限定されていたため、蓄財による老後設計を描いた高齢者には大きな衝撃となり得ます。本編では、制度の背景から影響試算、実施時期・対象・注意点まで、数字と図表を交えて徹底解説します。
💰 金融所得が社会保険料の対象に 📊
2028年頃から始まる新制度の影響と対策を徹底解説
📚 この記事でわかること
制度改正の背景と目的、公平性の観点からの必要性を詳しく解説
実際の計算例と負担増加額のシミュレーション
対象者の範囲と導入スケジュールの詳細
非課税制度への影響と情報連携の仕組み
今から始められる資産運用の見直しポイント
2028年頃を目処に、配当金や売却益などの金融所得が75歳以上の高齢者の社会保険料計算に反映される新制度が導入予定。
特定口座の取引情報がマイナンバーと連携し、市区町村へ共有されることで、保険料負担が年間数万円増加するケースも。
現時点でNISA口座は対象外とされており、制度への備えとして非課税枠の活用や資産運用の見直しが重要。
📱悩んだら、リサーチオンラインに相談して解決📱
この記事の目次
なぜ今、この話題?
制度改正の背景と目的
投資収益が社会保険料に紐づく!?
制度改正の全貌と今後の対策
なぜ今、この話題?制度改正の背景と目的
現役世代への保険制度の負担増
約30%
給与に占める社会保険料負担
(従業員+使用者負担)
現役世代への負担が継続的に重くなる構造が顕在化
高齢者支援の財源圧迫
1.7倍
75歳以上の後期高齢者支援金
(過去20年での増加率)
一方で本人負担は1.2倍程度にとどまり、制度の不公平感が拭えない
金融所得の過小評価問題
配当金・売却益の源泉徴収のみ行われ、確定申告不要
市区町村が所得を把握できず、保険料算出の対象外となっている
この"所得の未反映"が、制度改正で是正されようとしています。
どう変わる?制度改正の仕組み
どう変わる?制度改正の仕組み
証券会社から市区町村へ報告義務
-
特定口座の年間取引報告書を金融庁だけでなく、各市区町村にも提供
マイナンバーとの連携
-
2016年より、証券口座には個人のマイナンバーが紐付け済み
-
専用システムへの接続が可能であるため、情報連携が円滑
保険料算出方法への反映
-
金融所得が「年間の所得総額」に加算され、その結果、社会保険料が増
これまで反映されていなかった金融所得が社会保険料の算定基準に含まれることに
想定される負担増の実例
70代後半の単身者モデル
想定される負担増の実例
70代後半の単身者モデル
| 項目 | 現行制度 | 改正後 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 医療保険料(年間) | ¥170,000 | ¥220,000 | +¥50,000 |
| 介護保険料(年間) | ¥97,000 | ¥112,000 | +¥15,000 |
| 合計(年間) | ¥267,000 | ¥332,000 | +¥65,000 |
窓口負担の変化:
医療
介護
このケースでは、年間約6.5万円の負担増に加え、
介護保険の自己負担率も倍増します。
高齢者の株式益に新制度
2028年スタート予定の
社会保険料徴収とは?
対象者は誰?制度導入のスケジュール
75歳以上の後期高齢者
(国民健康保険含む)
65歳以上や医療保険加入の
会社員への拡大も議論されている
現時点では制度の外、
給与所得に基づく従来の算出方式が継続
実施スケジュール
政府目標
2028年頃の制度運用開始
前提条件
情報整備・システム構築・自治体調整が
スムーズに進んだ場合の目処
注意したいポイントまとめ 🛡
NISA口座は対象外
➜ 公式に明記されており、非課税口座の運用益は影響なし
金融商品の対象範囲
➜ 上場株式の配当金や売却益が対象。
非上場株式の配当金も含む見込み
税金との取り扱いの違い
- 税制度では確定申告が選択制
- 社会保険料制度では「年齢条件に応じて強制適用」が前提
社会保険料の新ルールに賛否
投資とどう向き合うか
議論されている課題と論点
「投資リスクを無視し強制徴収」への違和感
➜ 本来は"リスクを取って得た利益"という性質との整合性問題
社会保険制度の本質とのすり合わせ
➜ 労働者の収入に基づく保険という原則からの逸脱の是非
国際比較では稀な例
➜ フランス程度を除き、先進国では"金融所得の社会保険料反映"は珍しい
将来制度設計への示唆
➜ 経済同友会からも「マイナンバーと金融資産の情報整合を常識化すべき」という提言
今すべき対策アクション一覧
最新情報の継続確認
動向ウォッチは不可欠
2025〜2027年に制度詳細が固まる見通しなので、継続的な情報収集が重要
定期的な制度変更チェックを習慣化
高齢者世代の資産運用戦略見直し
最適化が鍵
対象金融商品や口座構成の最適化が鍵になる可能性大
ポートフォリオの再構築を検討
NISA活用の再検討
非課税枠の計画的活用
制度の抜け道として利用できるため、非課税枠の計画的活用が賢明
NISA枠を最大限活用する戦略立案
現役世代への影響はある?
現役世代への影響について
現役世代への影響は?直接的影響は限定的だが、将来的リスクも
現時点では会社員などの現役世代への直接的影響は限定的です。 制度の対象はまず75歳以上の後期高齢者で、 国保や後期高齢者医療制度の加入者に限定されており、 企業の健康保険に加入している会社員は含まれていません。
ただし、間接的な影響や将来的なリスクは存在します。 制度により高齢者の保険料負担が適正化されれば、 現役世代が拠出する後期高齢者支援金の軽減につながる可能性があります。 また、経済同友会などから「世代に関係なくマイナンバーで金融資産を把握するべき」との発言も出ており、 将来的に制度が現役世代へ拡大する可能性も否定できません。
現役世代は既に給与の約30%を社会保険料として負担しており、 今後の制度設計次第ではさらなる議論が必要になると考えられます。 短期的には直接影響を受けないものの、長期的視点での備えや情報収集が重要です。
FAQ|投資収益と
社会保険料制度改正について
FAQ:投資収益と社会保険料制度改正について
-
Q.1 高齢者だけが対象なのですか?
A. はい、現時点で制度改正の対象となるのは、主に75歳以上の後期高齢者です。政府はまずこの層から導入を始める予定ですが、将来的には65歳以上や他の年齢層へ拡大する可能性も示唆されています。現役の会社員などは、現時点では対象外とされています。
-
Q.2 NISA口座で得た利益も社会保険料に影響しますか?
A. いいえ、NISA口座は非課税制度のため、配当金や売却益が社会保険料の算定対象にはなりません。自民党の政策文書にも明記されており、対象外であることが確認されています。したがって、NISAを活用することで保険料負担増を回避できる可能性があります。
-
Q.3 どれくらい社会保険料が増えるのでしょうか?
A. ケースによりますが、70代後半で年金収入270万円+配当金50万円の単身者の場合、年間の医療・介護保険料が約6.5万円増加する試算が出ています。また、介護の窓口負担が1割から2割に上がるため、実質的な負担はさらに増える可能性があります。
-
Q.4 マイナンバーと証券口座の関係はどうなっていますか?
A. 2016年以降、すべての証券口座にはマイナンバーの登録が義務付けられています。このため、特定口座での取引情報を通じて、市区町村が金融所得を把握しやすくなっており、制度改正後はこの情報が直接社会保険料計算に活用される見込みです。
-
Q.5 制度改正に備えて、今から何をすべきですか?
A. まずは制度の最新動向を継続的にチェックすることが重要です。その上で、以下の対策を検討しましょう:
• NISAの活用や、対象となる特定口座での運用比率を見直す
• 金融資産の構成を再評価する
• 特に高齢者の方は、保険料や医療・介護負担への影響を踏まえた資産設計が必要
投資収益が社会保険料に
影響する時代へ
2025年の方針で、配当金や売却益などの金融所得が社会保険料の計算に反映される制度改正が進んでいます。75歳以上の高齢者を対象に2028年頃の導入が見込まれ、保険料が年間数万円単位で増加するケースも予想されます。
背景には、高齢者と現役世代間の負担の不均衡があり、公平性を確保するための改革とされています。証券口座とマイナンバーの連携により、市区町村が金融所得を把握しやすくなる仕組みも整いつつあります。
NISA口座は対象外ですが、非課税枠の有効活用や運用戦略の見直しが必要です。今後の制度の動向を注視し、資産設計を見直すことで、老後の安心を守る備えが求められます。
働く皆さんを応援しています!

あなたの資産形成を成功へ導きます
📊 投資の現状と課題
投資実施者の割合
まだ投資をしていない人
貯金重視の考えが根強い
😰 こんなお悩みありませんか?
政府は「貯金から投資へ」と言うけれど、何から始めればいいかわからない。iDeCoやNISAって聞くけど、複雑そうで不安...
✅ リサーチバンクが解決します!
iDeCoやNISAを活用した年金・税金対策の相談を提供し、多くの悩みを解決してきた実績があります。若いうちからの資産形成をしっかりサポート!
🎯 私たちのサービス
iDeCo相談
個人型確定拠出年金で老後資金作りと税制優遇を両立
NISA活用
少額投資非課税制度で効率的な資産形成をサポート
税金対策
節税効果を最大化する戦略的アドバイス
個別相談
あなたの状況に合わせたオーダーメイドプラン
📱 悩んだら、リサーチオンラインに相談して解決 📱
気軽に相談できる公式LINE「Research Online +Plus」を開設し、不安解消をサポートしています。
✨ 公式LINE登録のメリット