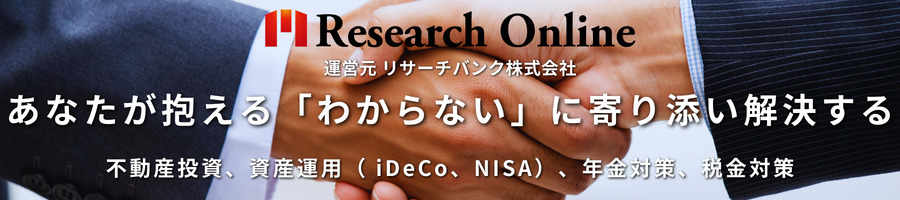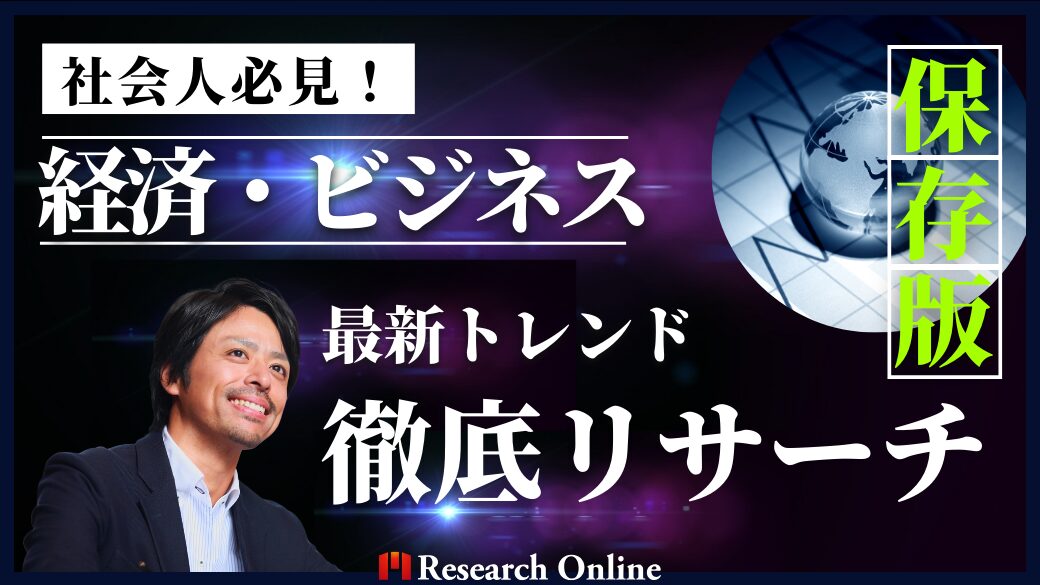「食品の消費税がゼロになるかも?」というニュースに期待を寄せる方も多いでしょう。しかし、実際には「消費税全体を5%に減税する」という案も浮上しており、どちらが家計や経済にとって有益なのかは一概に言えません。本記事では、これら二つの減税案の違いや影響を詳しく解説します。
-
食品消費税ゼロと5%減税の基本的な違い
-
各案を支持する政党とその政策背景
-
飲食店や消費者が受ける実務的な影響
-
減税による税収・社会保障への影響
-
どちらの案がどの層にとってメリットがあるか
▼リサーチオンライン編集部
記事の音声要約(1分)
📱悩んだら、リサーチオンラインに相談して解決📱
この記事の目次
減税案の比較
食品消費税ゼロ/消費税5%減税
政策の背景と支持政党
| 減税案 | 支持政党 | 主な目的 | 重視する層 |
|---|---|---|---|
|
食品消費税ゼロ
|
公明党、立憲民主党 | 生活必需品の保護 | 低所得者層、高齢者層 |
|
消費税5%減税
|
国民民主党 | 経済活性化、成長優先 | 中小企業、働く納税者 |
食品消費税ゼロ案は、生活必需品である食料品の税負担を軽減し、特に低所得者層や高齢者層の生活を支援することを目的としています。一方、消費税5%減税案は、経済全体の活性化を目指し、広く薄く課税することで中小企業や働く納税者の負担を軽減することを狙っています。
イデオロギーの違い
| 減税案 | イデオロギー | 考え方 |
|---|---|---|
|
食品消費税ゼロ
|
社会民主主義 | 必要なところだけ減税・免税する |
|
消費税5%減税
|
新自由主義 | 広く薄く課税する |
食品消費税ゼロ案は、社会民主主義的な立場から、生活必需品に対する税負担を軽減することを重視しています。一方、消費税5%減税案は、新自由主義的な立場から、経済全体の活性化を図るために広く薄く課税することを重視しています。
飲食店への影響
食品消費税ゼロの実務的な課題
食品の消費税をゼロにした場合、飲食店の税務にどのような影響があるのかを分析します
仕入れと販売の税率差による影響
食品の消費税がゼロになると、飲食店は仕入れにかかる消費税を控除できなくなり、納税額が増加する可能性があります。
| 項目 | 現状(10%) | 食品消費税ゼロ(仮定) |
|---|---|---|
| 仕入れ価格 | 1,000円+80円(8%) | 1,000円(0%) |
| 販売価格 | 3,000円+300円(10%) | 3,000円+300円(10%) |
| 納税額 | 300円−80円=220円 | 300円−0円=300円 |
| 利益 | 2,000円 | 2,000円(変わらず) |
現状(10%)の仕組み
食品消費税ゼロ(仮定)の仕組み
実務的な課題
- 飲食店の納税額が増加する(例では220円→300円、約36%増)
- 仕入税額控除の恩恵が受けられなくなる
- 利益は変わらないが、税負担が増えるため実質的な収益性が低下
食品消費税がゼロになると、仕入れにかかる消費税がなくなりますが、販売時には10%の消費税が課されるため、納税額が増加します。その結果、飲食店の利益は変わらないものの、消費者が「食品は消費税ゼロなのに価格が下がっていない」と感じる可能性があります。飲食店が価格を下げると、利益が減少するため、価格設定に悩むことになります。
線引き問題の発生
食品消費税ゼロ案では、以下のような線引き問題が発生します:
- コンビニで買って持ち帰る場合:0%
- 同じ商品をイートインで食べる場合:10%
- 調味料(例:みりん)の分類
このような線引きは、消費者や事業者に混乱を招く可能性があります。
消費税の捉え方
税抜き派 vs 税込み派

| 立場 | 主張 | 主な支持者 |
|---|---|---|
| 税抜き派 | 消費税は正しく転嫁されている | 財務省、経理担当者 |
| 税込み派 | 消費税は正しく転嫁できていない | 中小企業経営者、営業担当者 |
税抜き派は、消費税は最終消費者が全額負担しており、事業者は預かり金として受け取るだけであると主張します。一方、税込み派は、消費税は実質的に企業の売上税や第二法人税のようなものであり、力関係により価格に下げ圧力がかかるため、正しく転嫁できていないと主張します。
減税案のメリットとデメリット
食品消費税ゼロ案と消費税5%減税案の比較分析
食品消費税ゼロ案
メリット
- 食費の割合が大きい世帯ほどお得
- 「0%」という心理的インパクトが大きい
- 弱者救済の効果がある
デメリット
- 外食産業が不利になる
- 線引き問題が発生する
- 経済成長や景気回復の効果は薄い
- 税収が減少する
消費税5%減税案
メリット
- 経済全体の活性化が期待できる
- 中小企業や働く納税者の負担軽減
- 政府の関与を小さくし、経済を活発化させる
- 貿易を積極的に推進する
デメリット
- 税収の減少により、社会保障などの財源確保が課題になる
- 低所得者や高齢者などへの直接的な救済効果が薄い可能性がある
- イデオロギー的な対立を生む
- 輸出企業への影響が出る可能性がある
- インボイス制度との関係が不明確
比較ポイント
対象範囲
主な受益者
経済効果
食品消費税ゼロ案の詳細分析
メリット詳細
食費の割合が大きい世帯ほどお得
低所得者世帯や子育て世帯など、収入に対する食費の割合が高い家庭ほど恩恵を受けられます。特に、年金生活者や非正規雇用者などの経済的弱者に対する支援効果が期待できます。
「0%」という心理的インパクトが大きい
消費者心理において、「0円」や「0%」という表現は特別な効果があります。食品の消費税がゼロになることで、消費者の購買意欲を刺激し、食品関連の消費活動を促進する可能性があります。
弱者救済の効果がある
生活必需品である食料品の税負担を軽減することで、社会的弱者を直接的に支援できます。特に、食費が家計に占める割合が大きい低所得者層にとって、実質的な所得向上効果が期待できます。
デメリット詳細
外食産業が不利になる
食材は0%でも外食は10%のままとなるため、外食産業が相対的に不利な立場になります。これにより、外食産業の売上減少や雇用への悪影響が懸念されます。
線引き問題が発生する
「食品」の定義や範囲をめぐって複雑な線引き問題が発生します。例えば、菓子類や飲料、アルコール、調味料などをどう扱うかで混乱が生じる可能性があります。また、テイクアウトと店内飲食の区別なども課題となります。
経済成長や景気回復の効果は薄い
食品のみを対象とするため、経済全体への波及効果は限定的です。特に、高額商品や耐久消費財などへの消費刺激効果は期待できません。
税収が減少する
食品関連の消費税収入がなくなることで、国の税収が減少します。これにより、社会保障や公共サービスの財源確保が難しくなる可能性があります。
食品消費税軽減・ゼロ化を実施している国々
イギリス
基本的な食料品に対して0%の付加価値税(VAT)を適用しています。ただし、菓子類や清涼飲料などは標準税率が適用されます。
フランス
基本的な食料品には5.5%の軽減税率を適用しています。標準税率は20%です。
ドイツ
食料品全般に7%の軽減税率を適用しています。標準税率は19%です。
消費税5%減税案の詳細分析
メリット詳細
経済全体の活性化が期待できる
すべての商品・サービスを対象とするため、幅広い産業に恩恵があります。消費者の購買力が全体的に向上し、様々な分野での消費活動が活発化する可能性があります。
中小企業や働く納税者の負担軽減
すべての商品・サービスの税率が下がることで、中小企業の経営負担が軽減されます。また、働く世代の消費活動全般の負担も減少します。
政府の関与を小さくし、経済を活発化させる
税率を全体的に下げることで、民間の経済活動の自由度が高まります。これにより、市場原理に基づいた経済活動が促進され、経済全体の効率性が向上する可能性があります。
貿易を積極的に推進する
消費税率の引き下げにより、国内市場が活性化し、輸入品の需要も増加する可能性があります。また、輸出企業の国内調達コストも下がり、国際競争力の向上にもつながります。
デメリット詳細
税収の減少により、社会保障などの財源確保が課題になる
消費税は国の重要な財源であり、5%の減税は大幅な税収減少を意味します。これにより、社会保障や公共サービスの維持が困難になる可能性があります。
低所得者や高齢者などへの直接的な救済効果が薄い可能性がある
全体的な減税は、消費額の大きい高所得者により大きな恩恵をもたらす可能性があります。低所得者や高齢者など、消費額が少ない層への直接的な効果は限定的かもしれません。
イデオロギー的な対立を生む
消費税率の引き下げは、小さな政府を志向する新自由主義的な政策と見なされ、社会民主主義的な立場との間でイデオロギー対立を深める可能性があります。
輸出企業への影響が出る可能性がある
消費税は輸出時に還付される仕組みのため、税率引き下げにより還付額も減少します。これが輸出企業の資金繰りに影響を与える可能性があります。
インボイス制度との関係が不明確
2023年10月から導入されたインボイス制度との整合性や、制度変更に伴う事業者の負担増加などの課題が残ります。
消費税率引き下げの経済効果予測
GDP押し上げ効果
消費税5%引き下げにより、GDPが約1.5%程度押し上げられるという試算があります。これは、消費活動の活性化による経済効果です。
雇用創出効果
経済活動の活性化により、新たな雇用が創出される可能性があります。特にサービス業や小売業などでの雇用増加が期待されます。
税収への影響
短期的には約10兆円程度の税収減少が見込まれますが、経済活性化による法人税や所得税の増収で一部相殺される可能性があります。
FAQ|消費税ゼロと5%減税、
どっちが本当に得?
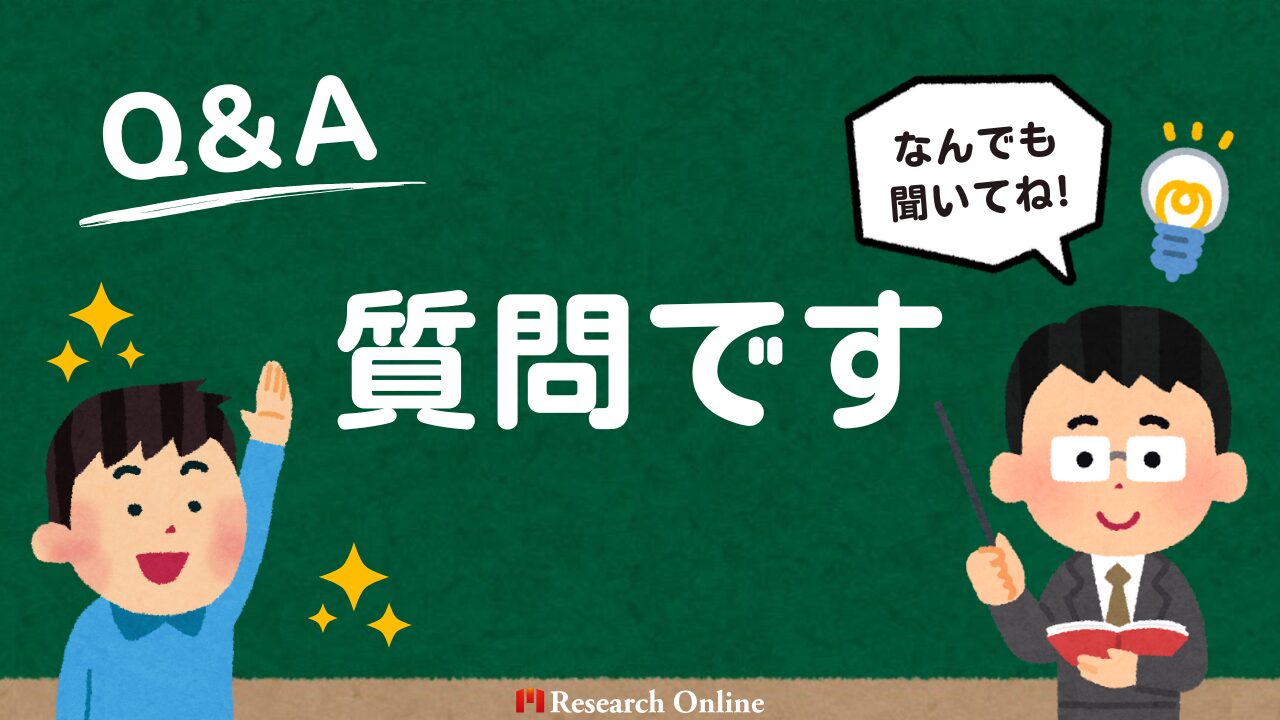
Q.1 食品消費税ゼロになると、
スーパーの価格はすぐに下がるのですか?
A. 一般的に「消費税ゼロ」と聞くと価格が下がると期待されますが、実際には仕入れ価格や販売価格の設定次第ですぐに価格が下がるとは限りません。特に加工品や外食は課税対象のままである場合も多く、線引きが曖昧な部分もあるため、消費者が実感できる値下げ効果が出にくい可能性があります。
Q.2 消費税5%減税の方が経済に
とって良いとされる理由は何ですか?
A. 消費税を全体的に5%に下げると、企業や個人の支出全般が軽くなり、消費が刺激されることで経済全体の活性化につながるとされています。中小企業の負担も減り、国内経済の成長エンジンを再点火する施策と見なされています。
Q.3 外食も「食品」なのに、
なぜ消費税ゼロの対象にならないのですか?
A. 外食は「サービス」に該当するため、たとえ食品を提供していても消費税ゼロの対象から除外される可能性が高いです。これは「テイクアウトとイートインで税率が異なる」という現行制度と同様の線引きであり、混乱を招きやすいポイントの一つです。
Q.4 減税によって税収が減ると、
社会保障に影響は出ないのでしょうか?
A. はい、減税による税収減は社会保障の財源確保に直接影響を与える可能性があります。特に消費税は社会保障財源の柱とされているため、どちらの減税案もその補填策が明確でなければ、年金や医療などのサービスに負担がかかる可能性があります。
Q.5 インボイス制度と
消費税減税にはどんな関係がありますか?
A. インボイス制度は、正確な税額の把握と納税管理を目的にしていますが、消費税率が下がると企業の事務作業の負担が軽減される可能性があります。ただし、5%減税にとどまる場合は負担軽減効果が限定的との指摘もあり、制度と減税政策の整合性をどう取るかが課題です。
公式LINEに今すぐ登録
「Research Online +Plus」は、ビジネスマンが気になる情報発信や、資産運用を行う際に直面する独自の課題を解決する環境を提供します♪
無料診断、相談を行なっていますので是非ともLINE登録して質問してください♪
📱悩んだら、リサーチオンラインに相談して解決📱
家計と経済にとって最適な選択は?

食品消費税ゼロ案と消費税5%減税案は、それぞれ異なる目的と影響を持っています。食品消費税ゼロ案は、生活必需品の税負担を軽減し、特に低所得者層や高齢者層の生活を支援することを目的としています。一方、消費税5%減税案は、経済全体の活性化を目指し、広く薄く課税することで中小企業や働く納税者の負担を軽減することを狙っています。どちらの案が家計や経済にとって最適なのかは、一概には言えません。個々の状況や価値観に応じて、慎重に判断する必要があります。
-
年金は「支払額に対する損益分岐点」を理解せよ
国民年金は約10年、
厚生年金は実質20年で元が取れる。 -
将来は70歳支給も現実的
制度変更により「損をする時代」が、
やってくる可能性が高い。 -
iDeCo・NISAで第二の年金を育てよう
自助努力こそが、老後の安心の最強武器。 -
副業や資産運用で“年金+α”の収入源を確保
月5万円の副収入でも生活は大きく変わる。 -
健康維持と就労延長が“最大の保険”
長く働ける体と習慣は、何よりも強い資産。
私たちは、働く皆さんを応援しています!

リサーチバンク株式会社は、iDeCoやNISAを活用した年金・税金対策の相談を提供し、多くの悩みを解決してきました。政府は「貯金から投資へ」のシフトを推奨していますが、全国調査では投資実施者は約3割にとどまっています。特に高齢者には貯金重視の考えが根強く、若いうちからの資産形成が重要です。そこで、リサーチバンクは、気軽に相談できる公式LINE「Research Online +Plus」を開設し、不安解消をサポートしています。
📱悩んだら、リサーチオンラインに相談して解決📱
公式LINEに今すぐ登録
「Research Online +Plus」は、資産運用を行う際に直面する独自の課題を理解し、それらに対応することで、自信を持って投資を行うことができる環境を提供します。将来を明るく過ごすために、まずは資産形成を考えましょう。相談はLINEから24時間いつでも無料で受け付けておりますのでお気軽にご相談ください♪